1. 「ポインタの配列」と「ポインタのポインタ」
前節で学習した「ポインタの配列」はポインタを使ってアクセスすることができます。 このポインタを「ポインタのポインタ」と呼びます。
#include <stdio.h>
int main(void)
{
char *mnthp[3] = { // ポインタの配列の宣言
"January", "February", "March"
};
char **p1, **p2, **p3; // 「ポインタのポインタ」の宣言
p1 = p2 = p3 = mnthp; // 「ポインタのポインタ」にポインタの配列
// の先頭番地を設定
// 例1
printf("** 例1の出力 **\n");
for (int i = 0; i < 3; i++) { // 「ポインタのポインタ」の値を変えずに
printf("%s\n", *(p1 + i)); // 相対的に文字列を出力
}
// 例2
printf("\n** 例2の出力 **\n");
for (int i = 0; i < 3; i++) { // 「ポインタのポインタ」の値そのものを
printf("%s\n", *p2); // 更新して絶対的に文字列を出力
++p2;
}
// 例3
printf("\n** 例3の出力 **\n");
for (int i = 0; i < 3; i++) {
int j = 0;
while(*(*p3 + j) != '\0') { // 「ポインタのポインタ」を使って、
printf("%c", *(*p3 + j)); // 1文字ずつ出力する
j++;
}
printf("\n");
++p3;
}
return 0;
}【実行結果例】
** 例1の出力 **
January
February
March
** 例2の出力 **
January
February
March
** 例3の出力 **
January
February
March
【例1と例2の解説図】
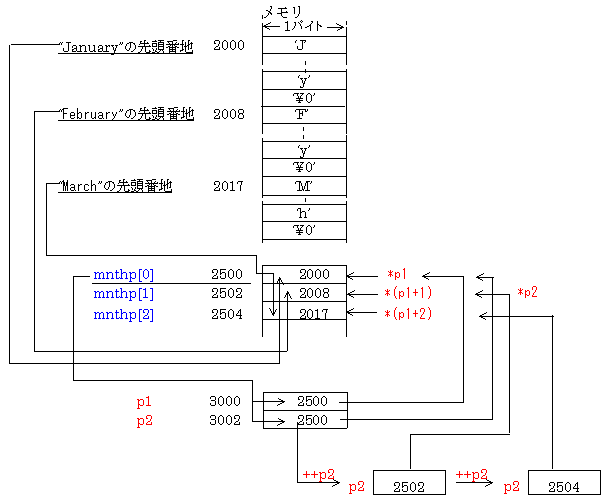
【例3の解説図】
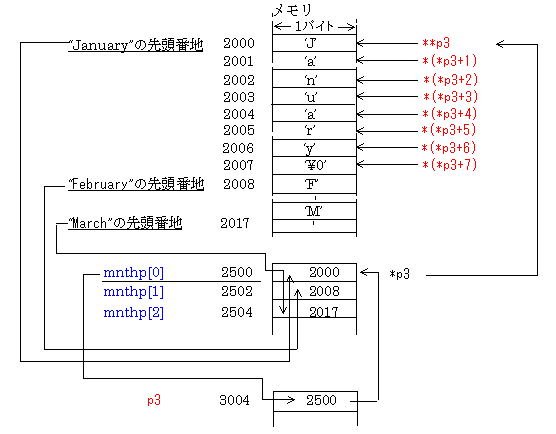
〇 演習問題
“Iizumi”,”Kanto”,”Kudo”,”Sato”,”Sugawara”,”Matuda”,”Wada”の7個の文字列の長さを求めて表示しなさい。
ただし、ポインタのポインタを用いること。
【実行結果例】
6文字 : Iizumi
5文字 : Kanto
4文字 : Kudo
4文字 : Sato
8文字 : Sugawara
6文字 : Matuda
4文字 : Wada
解答例
// 解答例1
#include <stdio.h>
int main(void)
{
char *name[7] = {
"Iizumi", "Kanto", "Kudo", "Sato",
"Sugawara", "Matuda", "Wada"
};
char **p;
int count;
p = name;
for (int i = 0; i < 7; i++){
for (count = 0; *(*(p + i) + count) != '\0'; count++);
printf("%2d文字 : %s\n", count, *(p+i));
}
return 0;
}// 解答例2
#include <stdio.h>
int main(void)
{
char *name[7] = {
"Iizumi", "Kanto", "Kudo", "Sato",
"Sugawara", "Matuda", "Wada"
};
char **p;
int count;
p = name;
for (int i = 0; i < 7; i++){
for (count = 0; *(*p + count) != '\0'; count++);
printf("%2d文字 : %s\n", count, *p);
++p;
}
return 0;
}// 解答例3
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(void)
{
char *name[7] = {
"Iizumi", "Kanto", "Kudo", "Sato",
"Sugawara", "Matuda", "Wada"
};
char **p;
p = name;
for (int i = 0; i < 7; i++) {
printf("%2d文字 : %s\n", strlen(*p), *p);
++p;
}
return 0;
}
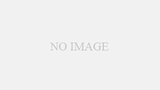
コメント